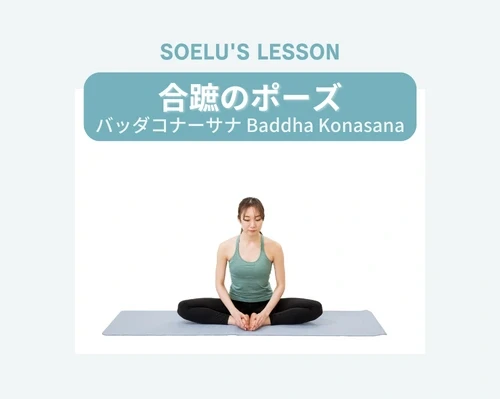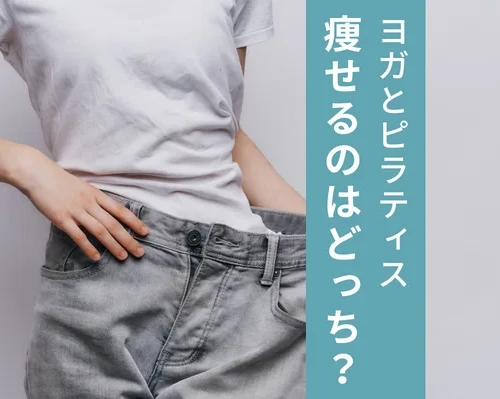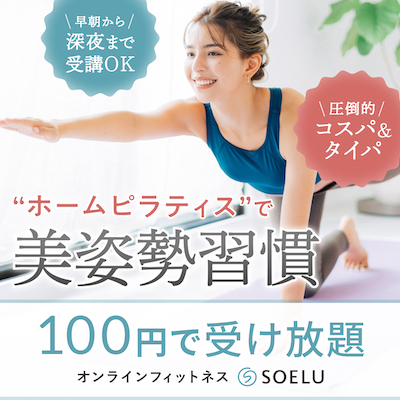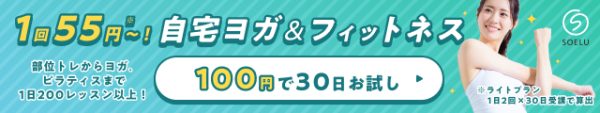【瞑想ヨガ】ラージャヨガとは?効果とやり方、意味をプロが徹底解説

ヨガスタジオのレッスンでなかなか聞く機会のない、ラージャヨガ。
現代で生きる私たちにも大切な教えがたくさん詰まった、ラージャヨガをヨガインストラクターの筆者がご紹介します。
おうちで本格スタジオレッスン!
ヨガをはじめるならオンラインという選択肢も!
SOELUなら、早朝5時から深夜までおうちでヨガレッスンを受講できます。
毎日レッスン開講、オンラインだから当日予約・すっぴんパジャマでの受講もOK!
\ 7月31日まで!お試し30日100円 /
体験期間中はいつでも解約OK!※
何回レッスン受講でも税込み100円
※お試し中に解約手続きを行わなかった場合、ライトプランに自動更新となります。
目次
ラージャヨガとは?

ラージャヨガは、瞑想によって自分自身を深く見つめるため、「瞑想のヨガ」といわれます。
ヨーガ・スートラというヨガの聖典に記載している「八支則(8つのステップ)」に沿って瞑想し、悟りに至ります。
ラージャの意味
ラージャとは、サンスクリット語で「王」の意味です。
心は王様のように、自分自身を支配しています。
というのも、心は、幸せと不幸せの両方を生み出す存在であり、自分にとって最大の味方でもあり、時には敵にもなるからです。
支配者のような心をコントロールするために、ラージャヨガで瞑想を行います。
ラージャヨガとハタヨガの違い
ラージャヨガは、瞑想がメインで、精神性にフォーカスしています。
しかし、ラージャヨガが目指すところの悟りの境地へ向かうには、難しい側面もありました。
そこで生まれたのが、体を動かすハタヨガです。
ハタヨガで体を動かすことで、瞑想に集中できる体づくりを行いました。
現在ヨガスタジオで行っているヨガのレッスンは体を動かしますよね。これらは、すべてハタヨガがベースになっています。
ハタヨガも最終的には瞑想を行いますが、呼吸やポーズといった肉体面のアプローチが大きい点が、瞑想メインのラージャヨガとの違いといえます。
ラージャヨガを実践してみよう

ラージャヨガの実践には、ヨガ哲学の理解が必要です。ヨガ哲学を理解してからラージャヨガを実践してみましょう。
ヨガの教科書「ヨーガ・スートラ」
「ヨーガ・スートラ」という本をご存知でしょうか?
ヨガをする人は、聞いたことがあるかもしれませんが、いわば、ヨガの教科書のような存在です。
ヨーガ・スートラは、紀元前4~5世紀に、パタンジャリ氏によって編集されたといわれています。
それまで、ヨガの教えは口頭で伝えられており、その内容をサンスクリット語でまとめた本です。
ヨガの教科書といっても、アーサナについての文章はごくごく一部で、心をコントロールする方法について書かれています。
ヨーガ・スートラに記載されているヨガとは、ラージャヨガです。ヨーガ・スートラの最初に、「ヨガは心の作用を止めること」だと定義しています。
すべてのヨガの目的は、心の波をコントロールし、心を鎮めることです。
色んな種類のヨガがありますが、すべて目的は同じで、そこへ至る手段が異なるだけ、ということになります。
生活の基盤から整える「八支則(アシュタンガ)」
ヨーガ・スートラは、瞑想を実践する方法として、「八支則(アシュタンガ)」について書いています。
八支則とは、瞑想で悟りの境地へ向かう、8つのステップです。
紀元前に書かれたものではありますが、私たちがすぐに実践できる、日常生活の教えから始まります。
【八支則については下記記事で解説しています▽】
【ヨガ哲学八支則の実践方法】人生のタメになる8つの教えとは
ポーズは坐位がメイン
八支則のアーサナは、「坐法」と表現されるとおり、座って足を組み行うものです。
アーサナとは、瞑想を深めるための体の準備。
瞑想をする時、「あぐらで座っているだけ」で簡単そうに思いますが、股関節が痛くなったり、背骨をまっすぐキープすることが辛くなってきたりしませんか?
瞑想中に体の方に余計な意識が向かないように、「安定して、快適にいられる体づくり」として、アーサナの練習を行うのです。
朝起きてすぐに実践できる!朝瞑想について詳しいやり方を解説しています。
関連記事:朝瞑想の簡単なやり方や効果【プロ解説】
ラージャヨガが向いている人
ラージャヨガは、ヨガ哲学を深めたい方や精神的な成長に興味がある方に向いています。よりよい人生を送りたいというのは、人間として当たり前の感情です。自身の感情をコントロールして、周りに影響されない自分を手に入れましょう。
まとめ
大昔にまとめられたヨーガスートラですが、日常生活での心得は、現代の私たちにとっても大切な教えですね。
自分の気持ち次第で、いつでも始められるところが魅力です。日常生活の中で行うヨガと、マットの上で行うヨガ。両方大切にしたいですね。
起きて5分、新しいヨガ習慣
「一年中冷えが気になる」
「首肩のこりがひどい」
だる重な寝起きからサヨナラ!
朝5時から始まるオンラインヨガで心身をのびのびとほぐしましょう!
リラックスヨガや寝ながらヨガなど、疲れが溜まった心身をほぐすヨガレッスンをご用意しています。
おうちで本格ヨガレッスンを体験してみませんか?
\ 7月31日まで!お試し30日100円 /
体験期間中はいつでも解約OK!※
何回レッスン受講でも税込み100円
※お試し中に解約手続きを行わなかった場合、ライトプランに自動更新となります。